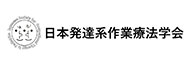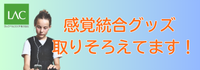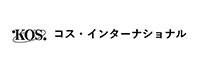大会長講演
3月15日(土)12:15~12:45
講堂
座長:伊藤 祐子(東京都立大学 健康福祉学部)
笑顔とつながりを育むこれからの作業療法
講師:森田 浩美(新宿区立子ども総合センター)
基調講演
3月15日(土)16:00~17:30
講堂
座長:森田 浩美(新宿区立子ども総合センター)
笑顔を目指す発達支援~これからの支援の在り方について~
講師:広瀬 宏之(横須賀市療育相談センター)
スペシャル企画
3月16日(日)9:00~10:30
座長:加藤 寿宏(関西医科大学 作業療法学科)
こどもの笑顔とつながりを作る仕組みと発達系作業療法とのつながり
こども政策全体の中での障害児施策について
講師:鈴木 久也(こども家庭庁 支援局障害児支援課)
こどもを育てることに携わる作業療法士として
講師:酒井 康年(うめだ・あけぼの学園・日本作業療法士協会)
シンポジウムⅠ
3月15日(土)12:50~14:40
講堂
座長:中島 そのみ(札幌医科大学 保健医療学部)
臨床につなげる発達系作業療法の評価
ASD、ADHD、DCDなど発達しょうがい児の作業療法評価
シンポジスト:岩永 竜一郎(長崎大学生命医科学域)
脳性麻痺について~ジジイになってしまった作業療法士からのメッセージ
シンポジスト:辻 善城(大阪赤十字病院付属大手前整肢学園)
進行性神経筋疾患における活動・参加を支える評価の視点と実践
シンポジスト:田中 栄一(北海道医療センター 神経筋/成育センター)
シンポジウムⅡ
3月16日(日)14:00~15:40
講堂
座長:東恩納 拓也(東京家政大学 健康科学部)
未来につなげる発達系作業療法の実践
脳性麻痺児・者の姿勢の特性を踏まえたADL支援
シンポジスト:米持 喬(大阪発達総合療育センター)
子どもの自己実現に向けた共創
シンポジスト:小玉 武志(北海道済生会みどりの里・発達支援事業所きっずてらす)
学齢期から成人期へ 参加と自律性を育む作業療法とは
シンポジスト:助川 文子(県立広島大学 保健福祉学部)
一般演題Ⅰ
3月15日(土)14:50~15:50
講堂
座長:仙石 泰仁(札幌医科大学 保健医療学部)
Ⅰ-1.
ADHDと二分脊椎の診断を有する児にCO-OPで立てた作戦を実行するための新たな作戦が有効だった症例報告
発表者:友田 直哉(社会福祉法人愛徳福祉会 大阪発達総合療育センター)
Ⅰ-2.
職場への本人理解を進めたことで就労の安定につながった事例
発表者:増子 拓真(TASUC株式会社)
Ⅰ-3.
強迫性障害と不器用さのある症例に対する不安のコントロール
発表者:松井 匠(医療法人桜十字 桜十字病院 リハビリテーション部)
Ⅰ-4.
運動学習の内省化によって投球動作の質的な改善が本人の自信へとつながった一症例
発表者:東海林 永遠(発達支援事業所 きっずてらす)
Ⅰ-5.
本人の主体性を育むチームアプローチ:中学1年生男児のシングルケース報告
発表者:奥川 純子(YUIMAWARU株式会社)
一般演題Ⅱ
3月15日(土)14:50~15:50
第2会場
座長:吉田 雅紀(北海道療育園)
Ⅱ-1.
手作りアイテムによって,外界へ気づきが広がり,自己表出が増えた重度重複障害者の一事例
発表者:神内 万土香(社会福祉法人愛徳福祉会 大阪発達総合療育センター)
Ⅱ-2.
段階的な賞賛が食事意欲向上と自食動作の定着につながった事例
発表者:伊藤 竜哉(北海道済生会 小樽病院 みどりの里)
Ⅱ-3.
重症心身障害児の思いが学校の先生に伝わるまで
〜保育所等訪問を通して個別療育の内容を学校へ繋げていく〜
発表者:前田 千智(株式会社リニエL リニエプラッツ阿波座)
Ⅱ-4.
自己決定の支援が作業遂行の達成につながったCO-OPを用いた取り組みについて
発表者:山本 柚葉(こども発達支援ルームPLANET)
Ⅱ-5.
3種類の関係性の理解学習~神経発達症児による研究から~
発表者:塙 杉子(名古屋女子大学)
一般演題Ⅲ
3月16日(日)10:40~11:40
講堂
座長:石附 智奈美(広島大学大学院医系科学研究科)
Ⅲ-1.
こどもの参加質問紙の縦断的測定特性:信頼性、反応性、解釈可能性
発表者:中村 拓人(神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリテーション学科)
Ⅲ-2.
自閉スペクトラム症の未就学児のメンタルヘルス:
Strengths and Difficulties Questionnaireの潜在移行分析
発表者:小塩 育(神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリテーション学科)
Ⅲ-3.
協調の困難さがある子どもに対する作業遂行への介入が子ども、養育者に及ぼす影響
発表者:勝原 勇希(森ノ宮医療大学 総合リハビリテーション学部 作業療法学科)
Ⅲ-4.
通常学級におけるOTと教員の協業の要素:質的記述的研究
発表者:三岡 莉子(北海道大学大学院 保健科学院 保健科学コース リハビリテーション科学科目群)
Ⅲ-5.
高等支援学校における学校作業療法の意義―師・教頭へのアンケートインタビューに基づいて
発表者:仲間 知穂(YUIMAWARU株式会社 こどもセンターゆいまわる)
一般演題Ⅳ
3月16日(日)10:40~11:40
第2会場
座長:中村 裕二(札幌医科大学 保健医療学部)
Ⅳ-1.
自閉スペクトラム症児における運動時の自律神経活動の変化~作業療法を継続した3名の1年後~
発表者:杉山 志保(静岡済生会総合病院 静岡済生会療育センター令和 療育技術科)
Ⅳ-2.
下じきの工夫が運筆操作へ及ぼす影響
発表者:村松 夏海(さいたま市総合療育センターひまわり学園)
Ⅳ-3.
限局性学習障害一事例に対する「算数障害のフローチャート」評価に基づいた支援とその効果について
発表者:伊藤 美希(社会医療法人北斗 北斗病院)
Ⅳ-4.
放課後等デイサービスにおける感覚統合療法の効果研究~身体機能面の評価結果の3項目~
発表者:奥田 歩(札幌医科大学大学院 保健医療学研究科 理学療法学・作業療法学専攻 感覚統合障害学分野)
Ⅳ-5.
感覚統合療法の視点を取り入れた小集団活動において家族に役だったことはなにか
~SCATによる分析~
発表者:佐々木 清子(東京保健医療専門職大学 リハビリテーション学部 作業療法学科)
一般演題Ⅴ
3月16日(日)13:00~13:50
講堂
座長:有川 真弓(千葉県立保健医療大学 リハビリテーション学科)
Ⅴ-1.
知的障がい者施設就労継続支援B型事業所におけるダンス活動の導入
~生活とステージに華を咲かせよう~
発表者:角田 実花(社会福祉法人こころみの会)
Ⅴ-2.
自閉スペクトラム症が疑われる子どもと家族の活動及び生活への参加の改善を目指した一例
発表者:石井 ハル(一般社団法人CIS)
Ⅴ-3.
小集団作業療法により食事と階段昇降の自立度が向上した幼児の事例
発表者:新井 七海(LIBOらぼ でんえんちょうふ)
Ⅴ-4.
保護者との協働により本人の「伝えたい」気持ちが育った事例
発表者:秋庭 伶香(TASUC株式会社 新宿早稲田教室)
総会
3月16日(日)11:50~
講堂
懇親会
3月15日(土)18:30~20:30
ホテルルートインGrand東京東陽町